先日訪れた「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」で心に残ったのは、建築家たちが「住まうことの意味」に真摯に向き合っていた姿でした。
特に、自らの理想を形にした“建築家の自邸”が、いかに創造の実験場であったかに強く惹かれました。
そんな思いを胸に、私が向かったのは――江戸東京たてもの園に移築された「前川國男邸」です。
江戸東京たてもの園
小金井公園内にある「江戸東京たてもの園」は、近代から昭和期の貴重な建築が集まる屋外博物館。
なかでも、建築家・前川國男の自邸は、住まいとしての美しさと思想を今に伝える建物です。
私は、桜咲く季節に久しぶりの再訪をしました。
(※アクセス情報・料金などは末尾にまとめてあります)
前川國男邸
建築家・前川國男は、ル・コルビジェ、アントニン・レーモンドの元で建築を学び、モダニズム建築の建築家として戦後の日本建築界をリードしました。

日本の近代建築の発展に貢献した建築家前川國男の自邸として、 品川区上大崎に1942年(昭和17)に建てられた住宅です。
江戸東京たてもの園HP
戦時体制下、建築資材の入手が困難な時期に竣工しています。 外観は切妻屋根の和風、内部は吹抜けの居間を中心に書斎・寝室を配した シンプルな間取りになっています。
切妻屋根の和風な外観ですが、中は2階まで吹き抜けの明るいリビングが広がります。
壁一面の窓の上部は格子窓、木製のせいでしょうか落ち着きと安心感が得られます。
格子が作り出す光と影のコントラストが美しく、私の一番のお気に入りの場所です。

ゆるやかな空間分け
ダイニングスペース


広さの中にロフト下で天井が低くなったこじんまり感のダイニングスペース。
ゆったりと落ち着いた会話と食事が楽しめそうです。
キッチンのドアを閉めれば、静かな作業スペースとして利用出来そう。
パソコンを開きながらコーヒーを、おうちカフェの出来上がりですね。
ソファコーナー

ソファと家具の高さを揃えることで目線が整い落ち着いた空間となっています。
仕事の打ち合わせ、友人を招いて楽しい会話、ゆっくり写真集を楽しむ休日、
妄想が次から次へと膨らみます。
階段コーナー

ゆるやかな勾配の階段は、静かに佇む造形の美、チェアとの一体感を感じます。
イサム・ノグチの照明が優しく照らして就寝前のレコードを楽しむのにぴったりな場所ですね。
このように、広いリビングでもゆるやかに空間分けされていながら、状況の変化に応じて柔軟な使い方もできそうです。
リビング・モダニティ展と照らし合わせて
展示で取り上げられていた7つの視点
――衛生、素材、窓、キッチン、調度、メディア、ランドスケープ。
前川邸には、それらのエッセンスが実に巧みに組み込まれています。
たとえば、白く清潔なタイルが印象的なキッチン。明るい窓辺に配されたガス台は、当時の「主婦の動線や気持ち」を丁寧に考えられていると思います。
リビングの大開口部も、素材の節約と心地よさの両立を試みた、時代の知恵にあふれた工夫でした。
家具や照明の選び方も、無理のないモダンさで暮らしに寄り添っていて。
こうして改めて見ると、前川國男という建築家の“住まいへのまなざし”が、この空間のすべてに息づいていると感じます。



「古い家の良さ」とは
建築の専門知識はありませんが、古い家を見ると「いいなぁ」と感じる理由ははっきりあります。
それは、光や風、自然との関わり方に“余白”があること。
たとえば、障子越しにやわらかく差し込む光や、庭の緑が映る木枠の窓。
時代の制約のなかでも、暮らしを少しでも豊かにしようとした工夫のひとつひとつに、心が惹かれます。
建築家たちがその時代にできる最大限の挑戦をした家は、
古さではなく、時間を超えて“美しさ”として今に響いてくる。
そんな発見の積み重ねが、私にとっての建築探訪の楽しみなのかもしれません。
江戸東京たてもの園の概要
江戸東京たてもの園には前川邸だけでなく、他にも貴重な古い建物が多く見どころ満載です。
昭和レトロな世界、どうぞお時間の余裕をもってじっくり楽しんでください。



●所在地
〒184-0005 東京都小金井市桜町3-7-1(都立小金井公園内)
042-388-3300(代表)
●入園料
一般400円、大学生320円、高校生200円、65歳以上200円。
ただし、未就学児、小学生、中学生は無料。
●アクセス
JR中央線武蔵小金井駅北口からバス5分
JR中央線東小金井駅北口からバス6分
西武新宿線花小金井駅南口からバス5分
▼詳しいアクセスはこちらから
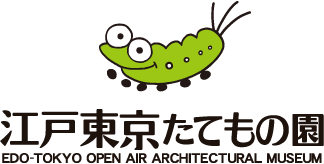
江戸東京たてもの園内にはカフェや食事が出来るところもありました。
▼ショップ&カフェの詳しい情報はこちら
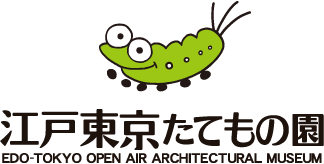



コメント